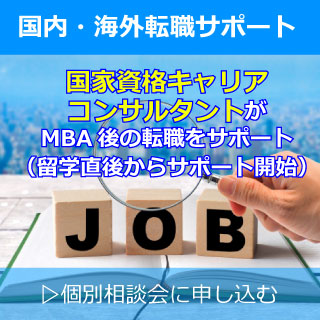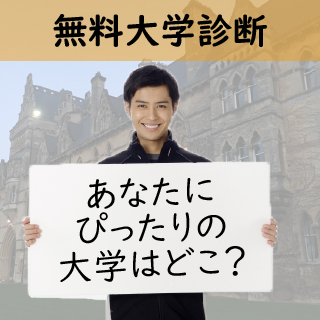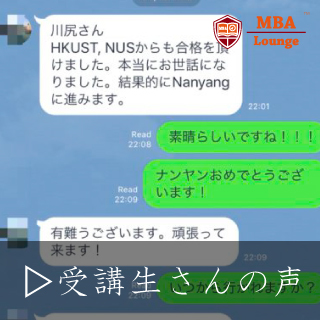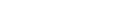復旦MBA(Fudan-MIT、中国)元木健太さんインタビュー
- 2025年2月15日
- カテゴリ:企業進捗
- タグ:

MBA Lounge受講生さんで、昨年中国の復旦大学MBA(Fudan-MITプログラム:復旦大学とMITの合同プログラム)を修了された元木健太さんにインタビューを行いました。
元木さんには、MBA体験や終了後のキャリアなど様々なお話を頂きました。
Q:MBA前はどんなお仕事をされていましたか?
MBA取得前は、経営企画部門で経団連対応などの渉外業務に従事しておりました。それ以前は、欧米のベンダーと協力し、新サービスの開発に取り組んでいました。これらの業務において、海外のパートナーと円滑にコミュニケーションを図るためには、単なる言語の壁を越えて、彼らの文化や価値観を深く理解することが重要でした。そのため、特に西洋の価値観に強く影響を受けながら業務を遂行する場面も多く、苦労も少なくありませんでした。
Q:なぜMBA取得を考えたのですか?
彼らの文化や価値観を深く理解するための手段として、多様な人種が集う海外MBAプログラムで膨大な課題に取り組む「他流試合」が当時の私には非常に魅力的な選択肢に映りました。ビジネスの世界に限定せず様々な背景を持つ人々と協力し、多種多様な課題に対して、あらゆる視点から問題を解決していくことで、グローバルな視点と柔軟な思考法を身につけることができると考えました。
Q:なぜFudan-MITを選択されたのですか?
今後、不確実性の高い環境下で高度な意思決定を行うためには、さまざまな事象の背景を理解し、正確な情報を得ることが重要だと考えました。例えば、当時はHUAWEIの急速な成長やそれに対する米国政府の対応など、複雑な国際情勢の中での正確な情報整理が求められていました。
現在、生成AIが世界の話題の中心となっていますが、中国の生成AIの実力を正確に把握している日本人は少ないと感じています。そうした観点からも、中国での学びは外せないと考えました。さらに、Fudan-MITプログラムでは復旦大学のMBAに加え、MIT(マサチューセッツ工科大学)との共同授業でMITのデュアルディグリーも取得できる点が非常に魅力的でした。
また、交換留学プログラムも充実しており、私はスイスでの交換留学を経験しました。結果的に、中国をはじめ、米国やヨーロッパの文化にも触れることで、広範なネットワークを構築することができました。この経験が、将来のビジネス環境において大いに役立つと確信しています。
Q:スイスでの生活について教えてください。
50~100か国の人たちと会話をすることができ、様々な文化に触れることができました。同じアパートには、アルゼンチン、チリ、ロシア、フランス、US、シンガポール、メキシコ台湾、中国、カナダからの学生がおり、多くの時間を一緒に過ごしました。
また、ちょうどそのタイミングで、ロシア、ウクライナの紛争が始まり、日本だとウクライナサイド一色ですが、世界全体を俯瞰してみると、そうではない価値観もあることを知りました。
また授業に関しては、かなり柔軟に履修が可能だったので、以前から興味のあった地政学やエネルギー関連の授業を大量に履修したのですが、欧州と日本ではここまで考え方が違うのか、と驚きも多かったです。
Q:プログラム全体を通じて、どんな刺激を受けましたか?
自分のビジネスを持ちながら、BATH(中国のハイテク企業4社:バイドゥ、アリババ、テンセント、ファーウェイ)のエンジニアとして活躍する友人や、中央政府を拠点にしつつ週末は地方で地域ビジネスに携わる友人たちから大いに刺激を受けました。
さらに、米欧中の状況を直接肌で感じることで、日本の発展に貢献したいという思いが強まりました。米欧中それぞれに独自の特徴があり、活気と勢いを感じる一方で、日本には依然として閉塞感があることも実感しました。こうした経験を通じて、日本の未来に向けた新たな視点と情熱を得ることができました。
Q:印象に残っているクラスメートについて教えて頂けますか?
一人は、台湾のレオ君です。レオ君の実家は台湾でファミリービジネスをしており、お兄さんがアメリカでお姉さんがカナダでそれぞれMBAを取得しているようです。
そこで、レオ君はなぜ復旦なのかを尋ねたら、家族で専門地域を分散しておき、台湾有事等の様々な政治リスクの影響を抑えるビジネス生存戦略の1つだと教えてくれました。そのような考え方もあるのか、ととても印象に残っています。
もう一人は、中国人のアシュリーさんです。彼女はアメリカの大学を卒業してアメリカの経営コンサルとして働いていたのですが、BATHの企業へ転職をするためのキャリア戦略でMBAを学ぶことにしたと教えてくれました。BATH入社にはMBA等、修士・博士が無いと難しいようです。彼女はその後中国のBATHの企業の一社に入社しました。
Q:MBAで思い出に残っている活動について教えてください。
復旦時代では、Thermo Fisher Scientific社での 6カ月間のインターンです。マッキンゼー出身の上司の部下として働き、ほぼ個別でビジネスの指導を受けられたことが大変勉強になりました。特に私のように1社でキャリアを形成してきた人間にとって、他社の考え方やビジネスの進め方に触れられた事は素晴らしい機会となりました。
スイスの交換留学時代では、「St. Galenシンポジウム」に参加したことです。
St. Gallenシンポジウムは、ダボス会議に類似したもので、スイスの政財界のリーダーが様々なトピックについて議論する場です。このシンポジウムには、ジュニアリーダーとして世界中から若手100人が招かれ、政財界のトップと1週間にわたり議論を行います。
特に印象深かったのは、チューリッヒ保険のトップと3時間にわたって民間保険会社のSDGsに対する取り組みについて討論する機会を得たことです。この貴重な経験を通じて、今後のビジネスに役立つ多くの知見を得ることができました。


Q:元木さんは、帰国後は何をされているのですか?
大きな変更が2つあります。
1つ目としてMBA前は経営企画業務に従事していましたが、より実ビジネスを動かすという目線から新ビジ系企画の部署に異動することになりました。研究開発マーケティング本部という部署で、そこでは新規事業創出の企画業務に携わる仕事をしています。
もう1つは帰国後も引き続き社費留学の派遣元企業で働く傍ら、副業で個人事業主として、経営コンサル業等の副業を開始しました。
日本の閉塞感の打開の為には、政財界で政策立案企画業務に引き続き取り組みつつも、自らも実ビジネスに入り込む両輪の活動が必要だと感じたためです。この意思決定にはMBA時代に出会った友人たちのバイタリティにも大きく影響を受けました。我が国の発展のためにはいずれかの活動がかけてもダメで、政策立案と施策実行の動きを同時並行で進めていくというのが重要という観点から以下のようないくつかの事業に取り組んでいます。
・斜陽産業企業の事業転換支援アドバイザー
日本には斜陽産業に属する企業がいくつかありますが、私はその中の1社の事業転換支援を行っています。こうした活動を通じて、日本の中小企業の生産性向上に貢献したいと考えています。
お茶文化の海外発信プロモーター
200年以上続くお茶屋の商品が日本人だけでなく、海外の方々にも魅力が届くようにするため、戦略策定から実際の施策運営まで、お茶屋の代表の方と二人三脚で取り組んでいます。伝統文化の発信も日本の発展には必要不可欠と考えています。
女性活躍支援企業のエバンジェリスト
日本の人口減少問題において、生産年齢人口を確保するためには女性の活躍推進が不可欠です。しかし、現実には共働きや育児の中でこれを成し遂げることは容易ではありません。こうした課題を解決するため、私は社会課題解決型のベンチャー企業でエバンジェリストとして、経営戦略から財務戦略までを担当しています。
・地方自治体の総合計画審議委員
地方自治体の総合計画審議委員として活動しております。地方創生という文脈において、自治体の発展(まちづくり)は必要不可欠です。そのため、自治体の総合計画の策定に民間企業の事業計画と同様の視点を取り入れ、市民の目線からより良いまちづくりに貢献したいと考えて取り組んでいます。
これらの副業もただその企業の発展という短期的ゴールではなく、これらの企業の発展を通じた弊社事業の新たなビジネス創出に関わるシナジー効果、加えてこれら事業の成功が周辺企業に波及して、我が国全体の発展に繋がればいいな、と考えて日々頑張っています。
政策立案という観点だと、ありがたい事にMBA卒業後から今まで色々と素敵なお誘いをいただいていますが、弊社でしか出来ない使命があると考えているので、弊社において全力で政財界と連携した政策立案に取り組んでいきたいです。そして政策立案と実ビジネス推進の両輪の活動を同時に実施することで加速させ、我が国の持続的な発展に貢献していきたいと考えています。